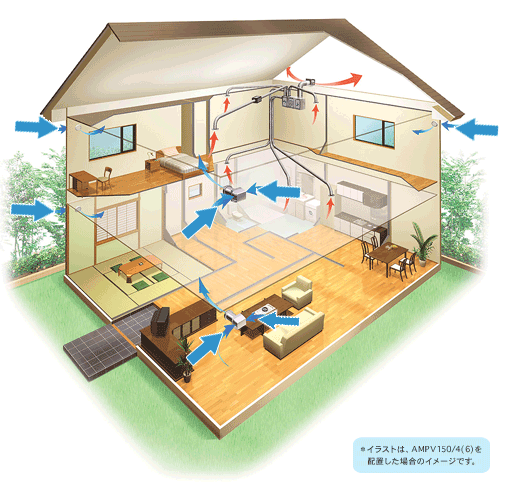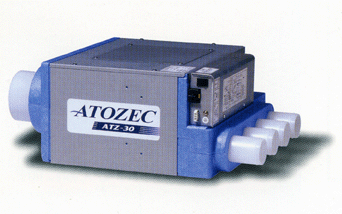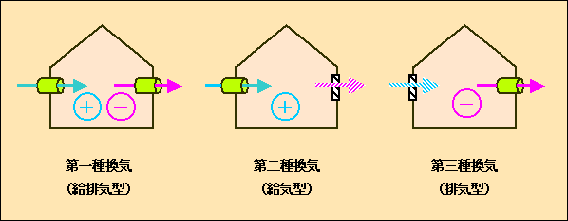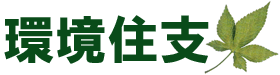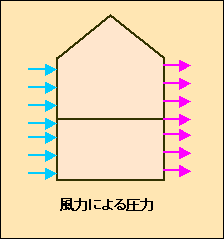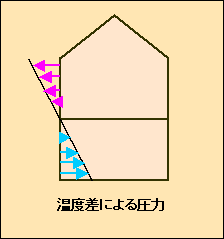ここにもう少し計画換気についての説明をしておきます。
前にも説明したとおり「常に」ということが安定の第一条件であり、24時間一年中同じ性能で換気し続け
なければなりません。
一年中回り続けるのですからランニングコストは当然安くならなければなりません。
また、静かでなくてはならないということも大切な要因です。
二つ目に「出入り口の明確化」が必要になります。
新鮮な空気は居室、寝室等から給気口を通じ取り入れられて、トイレや浴室のように水蒸気や臭い、粉
塵の出やすいところから外部へ排出することが必要です。
建物がある程度高気密化されると、給気口から入る外部の音がやたらと気になりますが、外部の通気層
を通じ建物の内部へ給気することで、音の出入りや風の影響を受けにくいように配慮しているビルダーも
います。
そして三つ目の「必要な換気量」ですが、これは次の三つの項目においてそれぞれ算出します。
第一に居住者の数による必要換気量で、一般には人間1人あたりで1時間に20〜30m3必要とされてい
ます。
4人家族で120m3/時とういうことになります。
ここで前の給気型の換気に戻りますが、−20℃の冷たい空気を1時間に120m3建物内に入れるという
ことが難しいのです。
冷たい空気は当然下に降りるので2・3階から排気するということがとても難しくなるのです。
第2に建物規模です。
これは建物の容積により、建物内の空気が何回入れ替わればよいかを示し一般的には1時間あたり0.5
回とされていますが、アメリカなどでは1時間あたり0.35回で計算されているようです。
第3の部位別による換気量ですが、これは空気が汚れたり、水蒸気の発生しやすいキッチン、浴室、トイ
レ、湿気や臭いのこもりやすい納戸等のの各部位で必要な排気量の合計になります。
必要な換気量をこれらの項目別に算出し、一番大きな数値を全体の換気量として設定します。
また、各部位の排気量を調節することで全体的な必要換気量を操作しています。
こうした換気の設定はいったん設定し設置してしまえばよいのですが、これらの機械的な部分だ けでは
補えないことがあります。
それは必要な気密性能を持ち合わせていることです。
どんなに素晴らしい換気装置でも隙間だらけの建物では計画は乱れてしまうし、排気型においては入口
はあちらこちらに出来てしまうわけで、これは実は計画換気というものが建物の気密性能の上に成り
立っているということなのです。
気密性能が高ければ高いほど計画換気は安定することになるのです。
「計画換気」とは高気密化がキーポイントであり、当然自然換気も高気密の上に成り立っているので
す。
やれ高気密だ中気密だ、中気密だから換気は必要ないだとかの討論は必要も無く、換気の本質を考え
れば住宅の気密化は必須条件なのです。
|